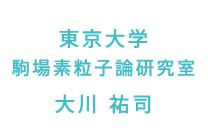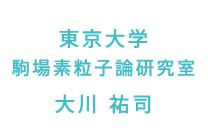

主要論文
-
Yuji Okawa and Tamiaki Yoneya,
"Multibody interactions of D particles in supergravity and matrix theory"
Nuclear Physics B538 (1999) 67-99 [hep-th/9806108]
超弦理論は平坦な時空では 10次元の理論ですが、type IIA と呼ばれる超弦理論は、相互作用が強くなると 11次元の理論になると考えられていて、その理論は M理論 (M-theory) と呼ばれています。M理論は、低エネルギー領域では 11次元超重力理論で記述されますが、超弦理論のような摂動的な定式化すらも知られていないミステリアスな理論です。その M理論が、0+1 次元の行列模型で定式化できるのではないか、という驚くべき仮説が1996年に提唱され、提唱者のイニシャルからその行列模型は BFSS 行列模型と呼ばれています。実際、BFSS 行列模型の one-loop 計算から超重力理論での 2体力が再現されるのですが、3体力を再現するべき two-loop 計算では超重力理論の相互作用が再現できないのではないかという論文が発表され、1997年から1998年にかけて大きな論争になっていました。この論文は私が博士課程 3年の大学院生であったときに、駒場素粒子論研究室の教授であった米谷さんと共著で発表したもので、とても複雑な行列模型の two-loop 計算を正確に実行し、超重力理論の 3体力が再現されることを示して論争に決着をつけました。私の博士論文はこの業績に基づいています。そして私はこの業績で、その後のアメリカでの postdoc としての研究への切符を手にしました。
-
Yuji Okawa and Hirosi Ooguri,
"Exact solution to the Seiberg-Witten equation of noncommutative gauge theory"
Physical Review D64 (2001) 046009 [hep-th/0104036]
超弦理論は、ミクロな世界での時間や空間に対する見方を根本的な変えなければならないことを示唆してます。一般相対性理論はリーマン幾何学に基づいていますが、超弦理論ではリーマン幾何学を拡張する必要があるかもしれません。その際、重要な役割を果たすのではないかと考えられているもののひとつに非可換幾何学があります。1999年に超弦理論の枠組みの中で非可換幾何学に基づくゲージ理論が実現できることが明らかになり、その後、この方面での活発な研究が行われていました。面白いことに、その非可換幾何学に基づくゲージ理論は、通常の幾何学に基づく別のゲージ理論としても表すことができて、両者を関係付ける写像は Seiberg-Witten map と呼ばれています。この論文は、カリフォルニア工科大学の教授である大栗さんに雇われてアメリカでの postdoc としての生活を始めた最初の頃に大栗さんと共著で発表したもので、その Seiberg-Witten map の厳密な表式を世界で最初に導出しました。ちなみに私たちがウェブに論文を発表した翌日、別の研究グループが Seiberg-Witten map の厳密な表式についての論文を発表し、約 2週間後にまた別の研究グループが Seiberg-Witten map の厳密な表式についての論文を発表しました。もちろん、この程度の発表日数の差は独立な研究成果と見なされますので重要ではありませんが、世界中の研究者としのぎを削り、より早く研究成果を得てより早く発表しようという気持ちは研究を進める良い motivation になっています。若い時期に競争の激しいアメリカで研究をすることができたことは、とても貴重な経験でした。
-
Nathan Berkovits, Yuji Okawa and Barton Zwiebach,
"WZW-like action for heterotic string field theory"
Journal of High Energy Physics 11 (2004) 038 [hep-th/0409018]
弦理論の非摂動的な定式化に向けて弦の場の理論と呼ばれるアプローチがあり、私はカリフォルニア工科大学での postdoc 時代の後半から弦の場の理論を集中的に研究し、弦の場の理論の世界的な権威である Barton Zwiebach がいるマサチューセッツ工科大学での次の postdoc の職を得ました。1986年に Witten がボソニックな弦理論での開弦の場の理論を構成し、1992年に Zwiebach がボソニックな弦理論での閉弦の場の理論の構成を完成させ、1995年に Berkovits が超弦理論での開弦の場の理論を構成しました。ボソニックな弦理論にはいろいろと問題があるのですが、超弦理論はそれらの問題を解消するように拡張したものです。重力は閉弦で記述されるので、超弦理論での閉弦の場の理論を構成することは重要な意味がありますが、Berkovits と Zwiebach と共著で発表したこの論文で、ヘテロ型と呼ばれる超弦理論での閉弦の場の理論の構成に成功しました。マサチューセッツ工科大学は、弦の場の理論の研究する上では最高の環境でした。
-
Yuji Okawa,
"Comments on Schnabl's analytic solution for tachyon condensation in Witten's open string field theory"
Journal of High Energy Physics 04 (2006) 055 [hep-th/0603159].
弦の場の理論の研究は、1999年に Sen と Zwiebach が Witten の弦の場の理論でタキオン凝縮という現象を表す数値的な近似解を構成してから大きく進展しました。その後、近似の精度は高められ、例えば level 12 という近似では、解のエネルギーの値は予言されている値の約 99.98% でしたが、解析的には運動方程式が解けないというもどかしい時期が続いていました。弦の場の理論の研究が落ち着いてきていた 2005年に、マサチューセッツ工科大学で一緒に postdoc をしていて CERN に移った Martin Schnabl が、解析解の構成に成功したというニュースが飛び込んできました。私もとても興奮して Martin Schnabl の論文を読んでいましたが、その難解な解の構成を解きほぐして行くと、解が K, B, c という3つの基本的な弦の場を構成要素として、それらが
[ K, B ] = 0, { B, c } = 1, c² = 0, B² = 0
という関係を満たすということと、BRST変換と呼ばれる変換で
QB = K, QK = 0, Qc = cKc
のように変換されるということだけで説明できることが分かり、この論文で発表しました。これらの関係式は KBc 代数と呼ばれ、その後の弦の場の理論の研究で重要な役割を果たしています。
-
Michael Kiermaier, Yuji Okawa, Leonardo Rastelli and Barton Zwiebach,
"Analytic solutions for marginal deformations in open string field theory"
Journal of High Energy Physics 01 (2008) 028 [hep-th/0701249].
Martin Schnabl による Witten の弦の場の理論の解析解の構成は大きなインパクトがありましたが、当時はそれがタキオン凝縮という特定の問題に対してのみ運動方程式が厳密に解けるということなのか、もっと普遍的な進展なのか分かりませんでした。2007年の1月に Barton Zwiebach と当時彼の学生であった Michael Kiermaier と MIT 出身でニューヨーク州立大学 Stony Brook 校の Leonardo Rastelli と共著で発表したこの論文で、マージナル変形と呼ばれる別の解析解の構成に成功しました。同時期に独立に Martin Schnabl も同じ解を構成しましたが、これにより普遍性のある進展であるという展望が開けてきました。さらにそれまでの解析解はボソニックな弦理論での弦の場の理論の解でしたが、2007年の4月に超弦理論での弦の場の理論の解析解の構成に成功しました。同時期に独立に Ted Erler も超弦理論での弦の場の理論の解析解の構成に成功しましたが、これにより進展がボソニックな弦理論にとどまらず、超弦理論に拡張できるという展望が開けてきました。(私はこの業績で第2回中村誠太郎賞を受賞しました。)また、それまでは簡単なクラスのマージナル変形に対してのみ適用できる解でしたが、Michael Kiermaier との共同研究で一般的なマージナル変形への拡張に成功し、さらに超弦理論への拡張にも成功しました。これらの一連の論文はドイツの Hamburg にある DESY という研究所にいたときに発表しました。理論部のスタッフメンバーとして任期5年の職に就いていましたので、ゆっくりとヨーロッパ生活を楽しむ予定でしたが、約1年間が経過したときに東京大学での任期なしの職に採用されて帰国しました。DESY では教育の義務はありませんでしたが、それまでの postdoc ではなくて staff member として研究室の運営にも携わり、研究面でも次々と良い論文を書くことができて充実していました。ちなみに当時 MIT の優秀な学生であった Michael Kiermaier とふたりで共同研究をしていたときは、Hamburg と Boston で時差が6時間あり、私が寝る前にその日の研究の結果をまとめて Michael にメールを書き、後はこのあたりの問題が解決するといいんだけど、というようなことも書いておくと、翌日、起きたときにその問題を解決した Michael からのメールが届いているという素晴らしい研究生活でした。
-
日本に帰国してからの研究については、後日、別のセクションで詳述する予定です。